西丹沢の関東大震災遺跡・遺構調査
山林が10%を超え崩落するとどうなるでしょうか。
砂防工学の専門家の話しでは壊滅状態に映るということです。
1923年9月1日の関東大震災はこの現象を丹沢山一帯にもたらしました。
10%から30%、秦野市付近はそれ以上でした。
その後の復旧事業は困難を極めました。
堰堤が整備されるのは1930年以降です。
地震発生から7年以上の年月が必要でした。
土砂崩れのため作業現場を設置できなかったのだと思います。

31日西丹沢の丹沢湖から西北に位置する大又沢一帯の調査をしました。
足柄の歴史再発見クラブの関東大震災遺跡調査委の一環です。
林野庁の東京神奈川森林署の全面的な協力を得ました。
署長さんら6人とクラブのメンバー7人の総勢13人で見て回りました。

堰堤の適地は沢がくびれている場所です。
上流部分には平らな場所があることが必要です。
見て回った堰堤はどこもこの条件に適合してました。
山林崩壊の中で立地場所を決定するのは容易ではなかったはずです。
当時の内務省や帝室林野局(宮内省部局)のレベルの高さをが伺えます。

驚いたのはきれいな石積です。
堰堤の上面がなだらかにカーブしているものもありました。
石工職人の技術の高さは感動ものです。城の石垣と同じです。
当時はコンクリートは普及してません。
現場近くの石を切り出し形を整え積み上げていきました。
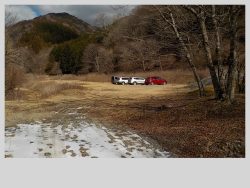
地蔵平という場所があります。
林野庁が管理している山林の中に突然平地が広がります。
名前の通りお地蔵さんが祀ってありました。
関東大震災と3年前の水害の犠牲者の慰霊碑がありました。
記録によれば地域の住宅は全滅状態でした。

この地域は林業が盛んでした。
1934年から62年まで地蔵平から浅瀬という地域まで森林鉄道がありました。
今は全く無人になってしまった景色を眺めるといとおしさを感じました。
松尾芭蕉なら「枯草や木こりどもが夢の跡」と詠んだでしょう。

気になったことがふたつあります。
林野庁が管理している山林と民有林の格差です。
林野庁管理の山林は間伐が行き届き美しいですが民有林は雑然としてました。
山林の荒廃は民有林で進んでいることが明らかです。
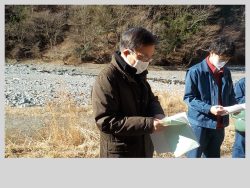
もうひとつは旧宮内省の建築物の管理です。
宮内省が所有していた堰堤などの所在が明確でないというのです。
戦後宮内省が廃止になったため引継ぎが十分でないことが原因です。
林野庁にも記録がありません。
関東大震災100年を契機にして実態の把握をする必要があります。

